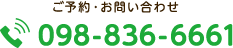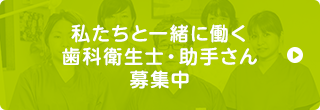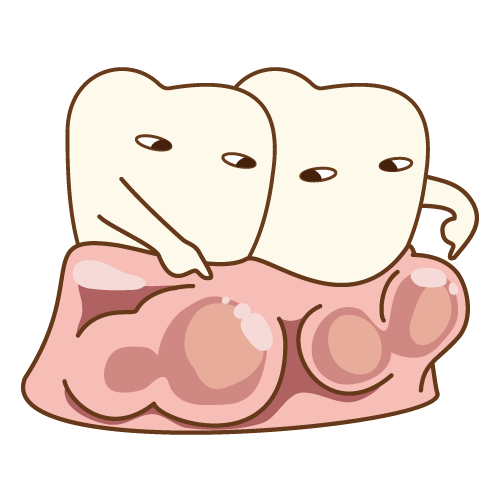 「口の中に硬いコブができたけど、これって何?」そう不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
「口の中に硬いコブができたけど、これって何?」そう不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、骨隆起の代表的な種類や原因、そして治療の必要性について、分かりやすく解説します。
骨隆起の種類や特徴
骨隆起は、主にできる場所によって名前が異なります。歯科医院を受診する前に、ご自身の症状と照らし合わせてみましょう。
1. 下顎隆起(かがくりゅうき)
これは、下の歯の裏側(舌側)にできる骨のコブです。左右対称にできることが多く、複数のコブが連なって現れることもあります。
2. 口蓋隆起(こうがいりゅうき)
上あごの真ん中、口蓋と呼ばれる部分にできる骨の突起です。最初は小さなコブでも、徐々に大きくなることがあります。
3.歯槽隆起(しそうりゅうき)
歯を支えている歯槽骨にできる骨の盛り上がりです。特に歯を抜いたあとの部位にみられることがあり、入れ歯やブリッジを作る際に邪魔になる場合があります。
大きさや形には個人差がありますが、歯肉の下に硬い隆起として触れるのが特徴です。
骨隆起の原因
骨隆起ができる主な原因は、まだ完全に解明されていません。しかし、多くのケースで以下の要因が関係していると考えられています。
遺伝
骨隆起は、遺伝的な要因が大きく関係していると言われています。親や兄弟に骨隆起がある場合、ご自身もできやすい傾向があります。
歯ぎしり・食いしばり
就寝中の歯ぎしりや、日中の無意識的な食いしばりは、歯やあごの骨に強い圧力をかけます。この過度な力が、骨を刺激して増殖させる原因になると考えられています。
噛み合わせの不調和
噛み合わせが悪いと、特定の歯やあごの骨にだけ負担がかかり、骨隆起の形成を促すことがあります。
骨隆起を放置するとどうなるの?
骨隆起は、通常、放置しても健康上の問題はありません。良性のため、がん化することもありません。しかし、大きくなると以下のような問題が生じることがあります。
入れ歯が作れない
入れ歯の土台となる部分に骨隆起があると、入れ歯が安定せず、痛みを生じる原因になります。
食事や発音への影響
大きな骨隆起は、食事中に食べ物が当たって痛みを感じたり、舌の動きを妨げて発音がしにくくなったりすることがあります。
歯磨きの妨げになる
歯ブラシが骨隆起に当たって出血したり、骨隆起の周りに汚れが溜まりやすくなったりします。
歯科医院で相談すべきタイミングと治療法
骨隆起を予防するためには、下顎隆起の原因となる過剰な力をコントロールすることが大切です。特に就寝時の歯ぎしり対策には、マウスピースの使用が有効です。
また、噛む力そのものが強くなくても、上下の歯が長時間接触しているとあごに負担がかかるため、「噛む時間を減らす」という意識も重要です。
骨隆起は、基本的に痛みや機能的な問題がなければ治療の必要はありません。しかし、以下のようなケースでは、手術による切除を検討します。
・入れ歯の作製を予定している場合
・食事や発音に支障をきたしている場合
・骨隆起が大きくなり、心理的な不快感がある場合